

|
私の最後の歩き遍路から、9年になる。 5日間でどこにするか思案した。 別格の慈眼寺を含むことにした。 いよいよ行けると決まると、ワクワクしてくる。 |
4月7日(金)晴れ
|
23時、名古屋駅発高松行きのJR夜行バスに乗り、翌朝5時10分に徳島到着。 徳島駅前のコンビニでおにぎりを買い、 |
4月8日(土)晴れ 立江駅から、第19番立江寺、番外「星の岩屋」、
ふれあいのさと坂本泊。 歩行距離 23.1km
| 6時9分に立江駅に到着。 駅から立江寺までは近い、方角が分からなくなり、 散歩中の人に道を尋ねると、案内をしてくれた。 誰もいない、静かな中で読経をし、ゆっくり寺の中を 見て回るうちに7時になったので 納経をお願いする。 桜が満開であった。 |

| ベンチで腰をかけている人がいた。 足を痛めたのでこれからどうしようかと悩んでいる とのこと。 焼山寺の遍路転がしで痛めたようだ。 折角、歩き遍路を始めたのに、 途中でつまずく人が出るのは残念だ。 お京塚は、鶴林寺への道とは逆方向であるが、 折角だからと思って尋ねた。 近いはずなのだが、場所が分からず、 1時間くらいウロウロした。 お京塚は、お京が改悛・出家して庵を結んだところ と伝えられているが、今は遍路小屋と、 遍路途中で亡くなった人たちの墓石があるのみ。 遍路小屋の中にいた、案内のボランティアのような人が説明してくれた。 |

| お京塚を後にして、星の岩屋へ向かう。 星の岩屋までは12.3km。 田植えが始まっていた。 途中、桜の花が咲き誇っていて、歩いていても 楽しくなる。 あるお宅の庭に咲いている桜が あまりに見事なので、写真を撮らせてもらう。 |

| 途中の沼江大師をお参りする。 いわれのあるお寺であるが、人気がなかった。 隣はこどものひろばになっており、昼間は子供たちで賑やかになるのであろう。 |

勝浦の町へ入ると花祭りの最中で、ひな人形や吊り飾りなので賑やかであった。 11時前であるが、もうすぐ星の岩屋への分岐点へ 差しかかる。 その前に腹ごしらえをしておかないと 食べ損なってしまう。 分岐点手前のあおき食堂は、「準備中」の札が かかっていたが、何でもよいからとお願いしたところ、 遍路ということで気を利かせてくれたのか 快い返事をもらった。 豚カツ定食を注文したら10分で出来上がり。 甘露煮の鮎も豚カツも旨かった。 まだ新しい洒落た店で、 バックグラウンドに洋楽を流していた。  勝浦川にかかる沈下橋を渡って、 星の岩屋を目指す。 目的地近くに小さなコンクリート製の橋がある。 幅が60cmくらい、橋の入り口は3段の階段下、 谷の深さは3mくらい。 前には気にかけなかったが、 今回は足がすくんでしまった。 慎重に思い切って渡ったが、 帰りはもう通りたくないと、 遍路道をやめて車道を通った。 厳粛で、幻想的な星の岩屋を 久しぶりに訪れることができて嬉しかった。  洞窟へ入り、しばらく瞑想していると、 雨が降り出し、厳粛さがさらに増した。   勝浦川の横瀬橋へ着いたのは15時。 今夜の宿泊先である「ふれあいの里さかもと」へ 確認の電話をすると、迎えに行きますと言われた。 1時間くらいで行けるだろうと思い、 断って歩いた。 着いたのは16時30分。思いのほか時間がかかった。 今夜の泊まり客は、一人歩き遍路6人。 数回の遍路経験者ばかりなので、 話題が豊富で話が尽きなかった。 |
4月9日(日)晴れ ふれあいのさと坂本から、別格第3番慈眼寺を往復。 歩行距離 16.8km
| 今日は慈眼寺のみを楽しむ。 ふれあいの里さかもとで、詳細な地図をもらい 丁寧に説明を受けたのでわかりやすい。 慈眼寺近くで、30代くらいの西洋人2人と 立て続けにすれ違った。 慈眼寺受付の話では、昨日の雨で濡れたので シャワーを貸してくれと頼まれ、 その夜は近くの無人遍路小屋へ泊まったようだ。 イギリス人とポルトガル人とのこと。 日本人以上に遍路慣れしていると驚いた。 慈眼寺に到着し、早速「穴禅定修行」を申し込む。 今、10人の団体が向かっているので 一緒に入るように急いで登ってくださいと言われる。 穴禅定参拝道の入り口には観音像の門があり、 その下を通って登る。  身につけているもの(輪袈裟、数珠、携帯電話等)は すべて外し、借りた白衣に着替える。 入り口で一人ずつ1本のろうそくを受け取り、 この明かりだけを頼りに真っ暗な穴禅定へ向かう。  穴は鍾乳洞でできているので、 |
4月10日(月)曇りのち雨 ふれあいのさと坂本から、第20番鶴林寺、第21番太龍寺、
第22番平等寺、民宿「山茶花」泊。 歩行距離 24.6km
| 朝7時、ふれあいの里さかもとの車で、 鶴林寺登り口まで送ってもらう。 私は横瀬橋の近くから、 ドイツ人女性は金子やの近くから登る。 登山道入り口には標石があり、 ここまで送ってもらったので、道に迷うことはない。  しばらく登ると「十町」という町石があり、 次々と町石が現れたのでわかりやすい。  「二町」が現れたので、 次は「一町」かと思っていたら、 目の前に突然、鶴林寺の門が現れてビックリした。  金子屋から登る道は門の正面の舗装道で、私はその右隣から登ってきたのであった。   鶴林寺を9時10分に退出。 太龍寺への道は延々と続く下り階段。 階段が終わったあたりに、トイレがあった。 旧大井小学校校舎のトイレを、 この校庭でゲートボールをしている人たちが 管理していて、歩き遍路にも使えるように していたのであった。 女性遍路にはありがたい存在だと思う。 入り口に納め札入れが用意されており、 私も納めさせていただいた。 那賀川にかかる水位橋から見る景色も雄大である。 山と川だけであるが、ありきたりとは思えない、 偉大さを感じる。 そんな景色に溢れている四国が好きだ。  水位橋を渡れば、すぐに太龍寺への登り坂となる。 相当登ったあたりで、最近の掃き掃除の跡がある。 さらに進むと、軽自動車の男性が 一人で落ち葉の掃除をしている。 「ご苦労様です」と声をかけると、 「危ないから掃除をしてくれと町に頼んでも 全然やってくれない」と怒りながら掃除をしていた。 『この先、道は細くなり車両通行禁止』とあるが、 軽自動車は除外らしい。 太龍寺で参拝している途中から雨が降り出した。 境内や、境内の桜も落ち着いた雰囲気を醸し出してくれた。  大師堂の近くに四角の箱がある。 天気がよければ、 この箱の向こうには鶴林寺が見えるはずだが、 今日はさっぱり。1 0年ほど前の箱とは形状が変わっていた。 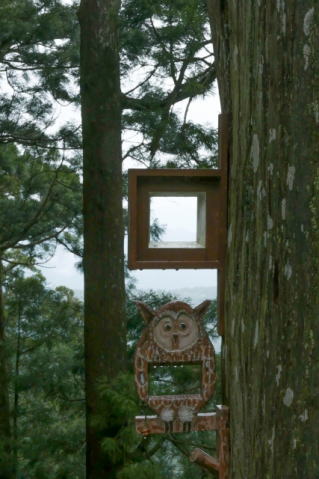 鶴林寺と太龍寺では、多くの西洋人に出会った。 彼らのほとんどは金剛杖をもち、 納経帳に納経をしている。 国も様々で、ベルギー、フランス、ドイツ、イギリス、 オーストラリアなどから来ている。 年齢も30代くらいから、 60代の夫婦まで様々であった。 観光地では、韓国、中国の人が多いが、 四国遍路では見かけなかった。 雨の中、納経所横の休憩所で弁当を食べ、 太龍寺を12時30分に退出。 太龍寺納経所にある案内地図には、 平等寺への道は舎心ヶ嶽経由の道しか載って いなかったが、 鶴林寺から通じている参道を少し戻り、 山門の外の三叉路を右へ折れる道をとった。 以前からの道で安心だと思った。 後で同宿した人の話では、どちらの道も時間的には全く変わりがなかったということであった。 山を下り、阿瀬比の交差点にある 遍路小屋で休憩を取る。  この交差点の向かい側のガソリンスタンドで トイレを借りようとしたら、故障中だと言われた。 確かに『故障中』の張り紙が添付してある。 同宿した人の話では、 店主が遍路にはトイレを貸さない 主義の人だそうで、 店員にもそのように教育しているということだ。 遍路に対する見方は、 四国の人たちの中でもいろいろあるのだなと 痛感させられた。 鶴林寺、太龍寺と500m級の山を二つ 上り下りしたあと、 平等寺への途中にはもう一つ200m級の山を 超えなければならない。 同宿の人たちには、 最後の山がきつかったという人が多かった。 私は、昇る速度は遅いが、 この山がそんなにきついとは感じなかった。 車道に出れば平等寺は近い。山門の仁王像が迎えてくれた。  平等寺では、4月8日より宿坊を始めた。 20番鶴林寺の手前の「金子や」 「ふれあいの里さかもと」から、 22番平等寺門前の「山茶花」までの間に 宿舎がない状態だった。 山茶花は満室になることがよくあり、 由岐の民宿まで足を運ぶ人もいた。 そんなところへ平等寺が宿坊を開設してくれたので、 少し助かるでしょう。 3部屋で個人では3人のみ、 二人組の場合で最大6人までとのこと。 今日、参拝したとき、宿坊開設の式典のための五色布がまだ残っていた。  本堂横の桜も満開であった。 平等寺横の山茶花へ宿泊。 今夜の宿泊客は、一人歩き遍路の男性2人、 女性2人、夫婦逆打ち歩き遍路の1組で、 私を含めて7人だった。 遍路経験者ばかりで、話題が豊富であり、 参考になることが多かった。 私が使った部屋は20畳で、独り占めだった。 雨降りだったので、部屋にビニールシートを敷き、 そこへ濡れたバックや傘などを置くように 準備してあった。 3日間歩き続けて、疲れがたまったのか、 足がジンジンとしてきて、なかなか寝付かれなかった。
|
4月11日(火)雨 民宿「山茶花」から、第23番薬王寺、薬王寺会館泊。 歩行距離 22.4km
|
大降りの雨ではないので、
|
4月12日(水)晴れ 薬王寺会館から、別格第4番鯖大師まで。 歩行距離 27.9km
 朝4時20分に起床、5時から朝食(握り飯)。 5時半に薬師寺本堂へ赴き、勤行に参加。 5時55分から始まり、約30分間。 勤行の後で僧が次のようなお説教をされた。 薬師寺は「発心の道場」の中で最後の札所。 発心とは、「発菩提心」の略。 誰でも心の中に仏心を持っている。 しかし、それに気づいていないので、 思い起こすことが必要である。 日頃の生活の中でも、仏心を思い起こしてください。  7時に薬師寺を出発し、 今回の最終目的地鯖大師を目指す。 60歳代の野球帽をかぶり、リュックを背負った男性が、 私を追い越しながら、 「しっかりした服装ですね」と 嫌みなような言葉を発していった。 菅笠、白衣、金剛杖の私を冷やかしたのだろうと思う。 彼にとっては、「歩くこと」が目的なのだろう。 私にとって「歩くこと」は手段なのだ。 同じように歩いていても全く違うと感じた。 1時間も歩くと暑くなり、日和佐トンネル入り口で、 半袖の下着と白衣の2枚にした。 道沿いに、大きな人形が並んでおり、 女性が二人話をしているようだった。 和む休憩所だ。  フランス人の男性が追い越しざま、 元気な声をかけてくれた。 私も元気よく、日本語で挨拶をした。 追い越した彼をよく見ると、 リュックのウェストベルト締めていなかった。 追いかけていって、 使っていなかったウェストベルトを使えるようにして、 締めてあげた。 楽になったと喜んでもらえた。 国道から少し昇ったところにある小松大師へ到着。  11時20分に牟岐の町へ到着。 以前の遍路で、駅前の民宿あづまに泊まったことがあり、 そこで食事をと思ったが廃業していた (11版の地図にはまだ記載)。 この町で見つけないと食いはぐれると思い、 ガソリンスタンドで尋ねて、喫茶店を紹介してもらう。 牟岐トンネルを越えてから旧道へ行くと、「大坂峠入り口」の看板が目についたので、大坂峠を行く。  「牟岐町観光ボランティアガイドの会」の説明板があり、それによると 牟岐町から浅川(海陽町)に至る「八坂八浜(やさかやはま)」は、12kmの間に、八つの坂と八つの浜があり、駄馬も通れない「親不知子不知」と言われ、波の荒い時は、道を洗い交通不便な難所で会った。「草鞋大師」から内妻の浜に下る小道が昔の土佐街道である。 大坂峠は、八坂八浜の最初の峠で、街道はそのまま残っている。峠の長さは、約1km、登り口は急坂であるが少し登ると平坦である。峠の高さは97m、そこに「内妻一里松」があり、そばに「草鞋地蔵尊」が祀られていた。一里松も枯れてしまい、地蔵尊も街道と旧・国道との交差点に移設された。峠から旧・国道への下り坂は急である。 松阪峠は、民宿・内妻荘のそばを通り、登ると差しかかる。杉林の中を登り、峠道は約500m、高さ60m、下り坂はいくつかの切り通しの間を抜けていく。頂上には「地蔵尊」(かずら大師)が祀られていたが、大正11年、旧・国道の完成で松阪トンネルの東口に移した。街道を通る人や、遍路さんが峠で休み、旅の安全を願って仏像を建てた。台座に「西中」と刻まれている。大正11年、旧・国道の完成で峠を通る人もなく落ち葉に埋もれていたのを現在地に移した。この地蔵さんも首を落としたのか、頭部と体が全く違った質の石である。  牟岐トンネルから、鯖大師までの間の 四つの坂を超えてくることができた。 松阪峠を抜けると海岸へ抜け、 しばらくは浜が遍路道となっている。 その海岸に座って休んでいる人がいたので、 私も隣で休もうと思ったら、西洋人だった。 オーストラリアから来て、 数年前まで豊橋で英会話を教えていた青年だった。 リンゴをかじっていて、 大き過ぎるので食べるか、と聞かれ、 少しいただくというと、別のリンゴを差し出した。 買い物袋に、リンゴ2個、その他の菓子箱など 多数が入っている。 たくさんの食べ物を持ち歩いているものだ。 リンゴを切ろうと思うが、ナイフは持っていないという。 私がカッターナイフを持っていることを思い出して、 これで切って1/4ほどいただき、一緒に食べた。  「へんろみち保存協力会」の『同行二人』地図には、 この遍路道の記載がなく、 日本人でもこのルートを通る人がほとんどいない。 なぜ西洋人が知ったのか尋ねたところ、 『同行二人』の英語版地図には載っているのだった。 英語版は、地名が漢字表記もあり、 歩き遍路にはこちらの方が利用しやすいようだ。  福良トンネル入り口手前を右に入り、 「土佐浜街道」を抜けていくと、 鯖大師の多宝塔横へ直接入ることになった。 「馬ひき坂」の表示がある峠は、 両側とも険しい坂で、 馬が荷を積んで昇ったり下ったりすることは、 到底不可能な急坂だ。 鯖大師のいわれが、本堂に説明図として掲げてあり、 その坂なのかと納得できる。  馬ひき坂を下って、鯖大師の境内へ。  鯖大師へ14時30分に到着。 住職の好意を得て、 夕方の勤行と夕食をあらかじめ予約して 了承を得ていたので、その前にゆっくりと参拝をした後、 境内を廻った。 今夜は宿泊客が少ないので、17時から夕食、 18時から不動堂で護摩焚きをする予定。 待ち時間に住職の話をゆっくり聞く機会もあった。 18時少し前から護摩焚きが始まった。 今日の宿泊客2人と私の3人が参加。 私は先祖供養をお願いした。 人数が少なくても、迫力のある護摩焚きだった。 お説教で次のように話された。 不動明王の前での護摩焚きは、不動護摩という。 恐ろしい顔をしているのも、悪に向かうため。 不動明王の右手の剣で、悪を払いのける。 左手の縄で、煩悩を縛る。 後背の火で、煩悩を焼き払う。 すべての悪魔や敵を撃滅し,信者を守護する。 徳島行きの電車は、18時39分。 その15分くらい前に終わったので、 急いで駅へ行き、乗り込むことができた。 徳島駅発の名古屋行き夜行バスの 発車時刻は、23時44分。 2時間半待たなければならない。 高速バスの待合所は22時で閉鎖となり、 居場所に困った。 歩き遍路は9年ぶりなので、少し心配であったが、 すべての計画が達成できて、大満足な遍路であった。 |
| HOMEへ | プロフィール | サイトマップへ | 次ページへ | 上へ戻る | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全コンサルタント | 技術士業務 | 騒音公害防止業務 | ISO支援業務 | 趣味の部屋 | |